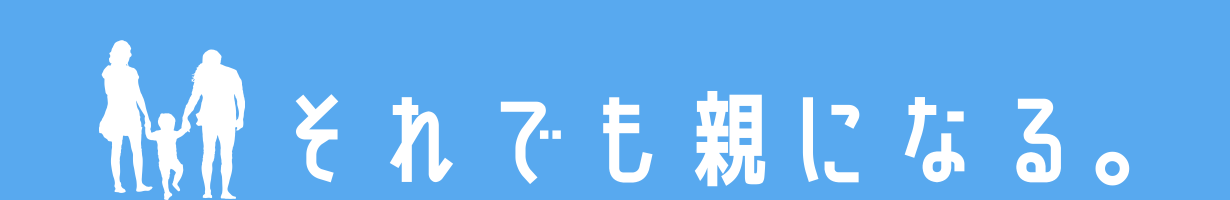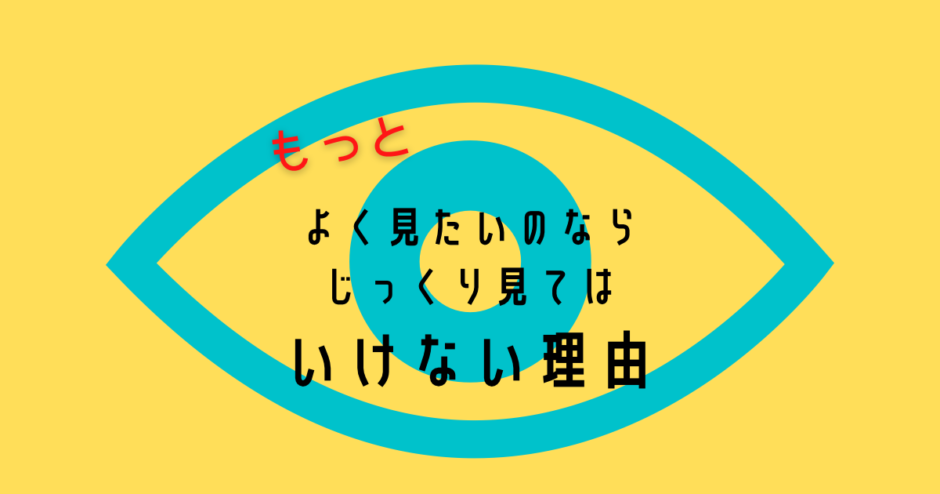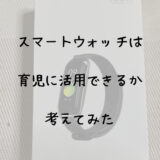こちらは、目視検査をする検査員さん向けの記事です。
「じっくり見る」ということについて、考えをまとめました。
目視で製品を検査する仕事を10年以上しています。
毎日たくさんの品物を目で見ていて、よく聞くのが
「じっくり(時間をかけて)見る」
という言葉です。
実は「じっくり見る」ことは、必ずしも「よく見る」ことにはなりません。
それどころか、目視検査においては見逃しが増えてしまう原因にもなり、逆効果であることのほうが多いのです。

いやいや、まさか逆効果って。でも時間をかけて見ないと心配だし。。。
はい。もちろん、どんなものにでも必要な検査時間はあります。
ただ、必要以上の時間をかけても、より検査できるわけではない、という話です。
これは「よく見る」仕事を長く続けていると、なんとなくわかってくることです。
でも突き詰めて理由を考えるひとは少ないと思います。
この記事では、適正な時間でものを見たほうが、効果が出やすいという理由をあげていきます。
- 最初はものを「見る」「じっくり見る」とはどういうことなのかを書いて、
- 次に多くの検査員が「じっくり見て」いるときになっている状態を紹介します。

目視検査をしているかたや、「ものを見る」ことについて興味があるかたは、ぜひ参考にしていってくださいね。
見るのに必要な時間は0.1秒
そもそも、ものを見るときに必要な時間って、どれくらいだと思いますか?
人間の網膜は1秒間に10回から数十回の信号を脳に送っています。
カメラでいえば、0.1秒に1枚以上の写真を撮影し続けている連写カメラです。
つまり、ひとがものを見るのに必要な時間は、0.1秒程度ということになります。
じっくり見ているとき、脳は無駄な処理をしている
例えば1分間、同じものを見続けたとき、脳は何をしているのでしょうか。
ひとがものを見るのに必要な時間は0.1秒程度ですから、実は残りの時間、作業としては、無駄なことをしています。
連写撮影みたいに、脳は同じ写真を何百枚何千枚と撮影し続けているんです。
スマホに同じ写真がたくさん入っちゃって、よく撮れた1枚だけ残して全部消去したりしますよね。
実は脳でもそれと同じような処理をするんです。
脳は送られてきた大量の全く同じ画像を、ほとんど消去します。
わざわざ同じ写真をたくさん撮って、たくさん捨てる作業です。
同じところをじっくり見ている検査員は、本当は何をしているのか
ここからは、検査の話です。
脳が無駄な作業をしているなら、目視検査中に同じところを「じっくり見て」いる検査員は何をしているのでしょうか。
ひとことで言うと、見ているのではなくて、考えています。
- 判断を迷っている
- 他のことを考えている
- そのほかの思考停止状態
違う場合もあると思いますが、まあ1分以上同じ面を見続けているようなときは、まずこの3パターンのいずれかでしょう。
判断を迷っている
合格にするのかどうか。あるいは書類を発行して他に判断を投げるのか。
「判断を迷う」場合は「判断基準があいまい」なのが原因です。
判断を迷っている瞬間に気づいたら、
- 限度が具体的に数字や限度見本で示されているか
- 上司や先輩からのダブルバインドはないか
などをチェックして、改善したほうがいいでしょう。
他のことを考えている
そもそも「判断しよう」というところまで行ってないのがこのパターンです。
主な原因としてマルチタスクが考えられますが、その他の原因で集中力が切れているのかもしれません。
思考停止状態になっている
判断を迷っているのでも、他のことを考えているのでもないのに集中できていない状態です。
1日の中で集中してパフォーマンスを発揮できる時間は限られています。
スピード感を意識したテンポの良い目視検査をして、限られた集中力を有効に使いましょう。
まとめ 適正な時間だけ見るのが大切
「じっくり見る」ことは、必ずしも「よく見る」ことにはならない理由をあげてきました。
- ひとがものを見るのに必要な時間は0.1秒程度
- じっくり見ているとき、脳は無駄な処理をしている
- 同じところをじっくり見ているときは、見ているのではなくて考えている
が理由です。
では、どう見れば「よく見る」ことができるのか? というと、
- 判断基準をはっきりとさせて、迷わなくていい状態にする
- テンポを意識して一定のリズムで見る
- 周辺視を活用する
などが効果的です。
それを見るのに適正な時間を考えることで、見ることの効率を上げることができます。

ちょっとマニアックな話でしたが、よかったら参考にしてみてください
それでは、また。
参加しています